最新記事:2015年01月15日更新
【女子力UP最新入浴法⑥ 】冬こそ差が出る「うるおい美人」
2015年01月15日更新
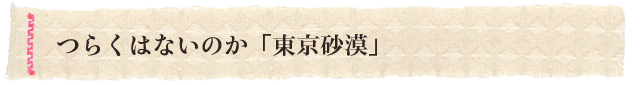
女子の冬の悩みの代表的なものの1つに乾燥がありますよね。
オッサンの僕にしても年々背中や腰のまわりのかゆみを実感しています(...加齢のせいともいう)。12月から1月にさしかかると、乾燥でかゆみが強くなり、ついつい肌にダメージを与えてしまうこともあるのではないでしょうか。
実際に気象庁のデータによると、東京の2014年1月の平均湿度は46%。1914年は61%ですから、100年間で湿度が15%下がっていることになります。ちなみに気温は2014年1月7.9℃、1914年1月4.3℃で、100年間で3.6℃の上昇。湿度減の要因の一つは温暖化ともいわれています。
往年のヒット曲に「東京砂漠」がありますが、ほんとうに東京の砂漠化は進んでいるのかもしれません。
まてよ...、ということは、現代の女子より100年前の女子の方がしっとりした美肌だったってこと?
ちょっと100年前にタイムスリップしてみたいような...、いやいや、 テクノロジーの進んだ現代、100年前の女子に負けるわけにはいかないじゃありませんか。
思いつくのは加湿器!
...ううん。僕の子供のころは、石油ストーブの上にやかんでお湯沸かしてたなぁ。
まあ、お風呂の話にまいりましょう。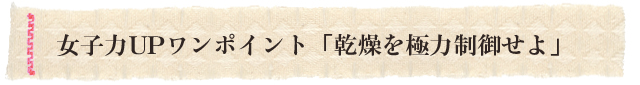
「お風呂」場面における乾燥予防は、いかに浴後の「水分蒸散量」(皮膚から失われる水分量)を少なくするかにかかっています。
基本は、
① 体を洗うときは「ゴシゴシこすらない」
② 冬仕様の入浴剤を
③ 浴後の保湿は入念に
がポイントです。
まず①。これは年間を通して言えることでもありますが、体を洗う際に「ゴシゴシ」こすってしまうと皮膚にダメージを与えてしまいます。毎日お風呂に入るのであれば、日常生活で体を清潔に保つには、やさしくなでる程度で十分です。
②に関しては、硫酸ナトリウムなど保温機能が高いものを選んでみると良いでしょう。
そして③。女子であれば常識中の常識ではありますが、冬ならではのポイントを、アロマ研究家で温泉利用指導者でもあるケイ武居さんにうかがいました。
「お風呂上りには、いつものアイテムを使う前に、ワンクッション、オイルマッサージを挟んでみると効果的です。フェイシャル、ボディともに週2回程度のセルフマッサージを試してみてはいかがでしょうか。乾燥がひどい方は集中的に毎日実践してみるのもいいかもしれません。油っぽいのが気になる方は、マッサージ後ホットタオルで蒸しあげると、オイルの吸収も促進しますし、べたつき感も解消できますよ」
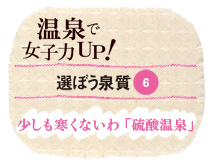 今回ご紹介するのは、硫酸塩泉。ワンポイントでもふれましたが、浴用の適応症には、ズバリ「皮膚乾燥症」。硫酸ナトリウムが、皮膚のタンパク質と結合して膜を形成するので、保温効果が高いというのがその理由。今回のテーマにぴったりでしょう!?
今回ご紹介するのは、硫酸塩泉。ワンポイントでもふれましたが、浴用の適応症には、ズバリ「皮膚乾燥症」。硫酸ナトリウムが、皮膚のタンパク質と結合して膜を形成するので、保温効果が高いというのがその理由。今回のテーマにぴったりでしょう!?
ほかには、きりきず、末梢循環障害、冷え性、うつ状態も適応症。初回にご紹介した塩化物泉も浴用では同じ効果があるとされています。
飲用では、胆道系機能障害、高コレステロール血症、便秘が適応となっていますので、飲泉許可のある場所でお試しください。
冬に試してみるなら、雪景色も楽しめる蔦温泉(青森県)、山代温泉(石川県)なんていかがでしょう。ヒートショック(居室と浴室の温度差が血圧の急変動を引き起こす)に注意は必要ですが、寒いときには寒さを追求するのも楽しくありませんか?「うるおい美人」を目指すには、湿度が高い事も好印象です。
(注:体調を崩してらっしゃる方、ご高齢の方にはおすすめできません)
蔦温泉は、源泉の真上にヒバで作られた味わいのある浴槽が圧巻。ヒバの底板からふつふつと湧き出る源泉「わき流し」の湯は、温泉ファンを魅了しています。味わいたいのは青森地鶏のシャムロック。ここを拠点に秋田(比内地鶏)、岩手(南部どり)、福島(伊達鶏)とまわれば「みちのく〜地鶏旅〜」でしょ?(...わかる人いるのかなあ)  山代温泉は開湯 1300年。温泉街は、共同浴場「古総湯」、「新総湯」を中心に、「湯の曲輪(ゆのがわ)」と呼ばれる街並みが風情豊かに形成されています。
山代温泉は開湯 1300年。温泉街は、共同浴場「古総湯」、「新総湯」を中心に、「湯の曲輪(ゆのがわ)」と呼ばれる街並みが風情豊かに形成されています。
朝6時にオープンする「古総湯」では、一番に入浴すると(男女各1名)、「壱番湯札」をもらえますので、ゲットしてみてはいかがでしょうか。もちろん僕もゲットしましたよん(自慢...笑)。
味わうのはもちろん「かに」。ズワイガニの雌の「せこがに」は、小さいけれど、内子、外子、かに味噌が凝縮。お酒がすすむことうけ合いです。
雪見酒としゃれこみたいところですが、お風呂の中ではダメヨ〜ダメダメ。
