最新記事:2017年05月25日更新
【第12回】世界に向けて日本のシードルを情報発信!長野シードルコレクション
2017年05月25日更新
今回は、初の長野シードルコレクション開催に合わせて、世界的に有名なシードルジャーナリストのBill Bradshaw氏が来日し、日本のシードルを世界に伝える取材ツアーに同行しましたので、長野シードルコレクション当日の様子と合わせてご紹介いたします。
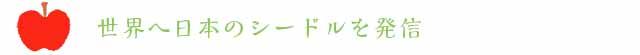
Bill氏の訪日は、2017年5月17日から19日の3日間かけて長野県各地の生産者を訪問し、20日(土)に長野県飯田市で開催された「ナガノシードルコレクションin飯田」への参加、その翌日21日(日)の「ナガノシードルセミナー」にて、国内のリンゴ農家やシードル生産者に、より世界で評価される質の良いシードル作りに向けた提言を頂くため、NPO法人 国際りんご・シードル振興会が企画しました。長野県内のリンゴ果樹園やワイナリー、シードル醸造所を訪問した3日間のうち、2日目の長野県北部の取材から同行させていただきました。
今回、同行した訪問先は以下の通りです。各訪問先で特に印象に残ったことをも合わせてお伝えします。
・楠ワイナリー(須坂市)
ふじ100%で作るシードル「りんご名人」を試飲しました。地下室の貯蔵庫で2年熟成させることで熟成香が引き出されたシードルを口にしながら、ワイナリー設立とシードルづくりについてのインタビューからスタートしました。Bill氏は、イギリスCiderの伝統や日本との違いを丁寧に説明してくださいました。 ・一里山農園(飯綱町)
・一里山農園(飯綱町)
「一里山シードル」の原料となるリンゴの果樹園を視察しました。昔ながらの幹が太い普通栽培のリンゴの樹(高さを抑えて横に広げる仕立て方)に、まずは日本とイギリスの違いを感じたようです。イギリス・サマセットでは果樹園で動物たちを大切に育てる文化があり、受粉のために飼っている日本ミツバチの巣箱の前で話が盛り上がりました。Bill氏と別れる際に「ミツバチを大切にしてください」と一言添えられたことで、サマセットの人としての心に触れた気がしました。 ・いいづなアップルミュージアム(飯綱町)
・いいづなアップルミュージアム(飯綱町)
飯綱町の小澤副町長や学芸員の小山さんから、飯綱町のりんごの歴史とシードルにも使用される和りんご「高坂林檎」のストーリーをご紹介しました。昔、8月頃に神仏へのお供えものや庶民のご馳走として親しまれていた高坂林檎は酸味や渋味が強く、1987年には高坂地区に1本残るだけとなりましたが、今では飯綱町のシードル用として復活したと聞いたBill氏は、そのストーリーがシードルの魅力に大きく貢献すると伝えていました。 ・サンクゼール・ワイナリー(飯綱町)
・サンクゼール・ワイナリー(飯綱町)
訪問した翌週に初蒸留をするシードル・ブランデーの蒸留機を視察し、その原料でもある高坂林檎やイギリス原産のクッッキングアップルであるブラムリーを使った「いいづなシードル」を試飲しました。日本では珍しいシードル用リンゴのビター・シャープに該当する品種を使ったシードルが日本で出会えたことに、Bill氏はやや興奮気味でした。 ・カモシカシードル醸造所(伊那市)
・カモシカシードル醸造所(伊那市)
信州大学と提携しシードル用に育てているリンゴの圃場見学を見学し、酸化を極力避けて作る「カモシカシードル」を試飲しました。イギリスの伝統的なCiderは、果汁を酸化させることが必須であるため、その理由や味の違いをじっくり確かめていました。そば粉のガレットとのペアリングがこの日のランチ。 ・ASTTALシードルクラブ&伊那ワイン工房(伊那市)
・ASTTALシードルクラブ&伊那ワイン工房(伊那市)
伊那市の飲食店30店舗で立ち上げたASTTALシードルクラブ誕生の理由と、20種類の品種をブレンドした果汁をあえて酸化褐変させて複雑味を出したオリジナルシードルのコンセプトと製法を、クラブの代表である渡邉さんと醸造を担当する伊那ワイン工房の村田さんから話を聞きました。その作り方は、今回の訪問先の中では、もっともイギリスの伝統的な製法に近いそうです。 ・信州まし野ワイン(松川町)
・信州まし野ワイン(松川町)
りんごや洋梨を24種類ブレンドし、先日発売したばかりのピオニエシードルやまし野シードル、発泡の無いりんごワイン、りんご農家の委託シードルをテイスティングしました。イギリスの伝統的なCiderは、発泡性の無いStill Ciderが多く、今回初めて口にしたリンゴの香り豊かなりんごワインにも興味を示していました。試飲の後は、子ヤギが生まれたヤギ牧場も見学しました。
Bill氏の出身地であるイギリスのサマセットで作られる伝統的なCiderは、生食用では無いCider専用のりんごのみを使い、自然酵母の力を借りて作られます。発酵の過程で、様々な酵母やバクテリアが働き、Ciderに甘みや酸味、渋みといったリンゴ由来の味わいだけでなく、時にはスパイシーで複雑な味わいを持っています。
「複雑味をゆっくり味わうことで、そのCiderが生まれた背景が見えてきます」とBill氏は言い、とても集中して時間をかけながらテイスティングを行う姿が印象的でした。
自然酵母は、日本で主流の培養酵母に比べて発酵の管理が難しくリスクが伴いますが、イギリスでは長年研究を続け、自然酵母でも管理ができることが分かってきたそうです。イギリスと日本では、リンゴの品種も自然に存在する酵母も違うため、その研究結果をそのまま使用することは難しいですが、気になる醸造家の方も多いのではないでしょうか。
一方で、日本のシードルに足りないのは、りんごの渋みとシードルの複雑味。そして、世界から注目されるには、フランス語の「Cidre」(シードル)ではなく、英語の「Cider」(サイダー)と名称を変える必要があることを、各所でアドバイスいただきました。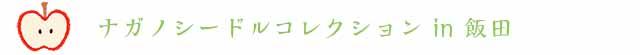
 Bill氏の訪問先のゴールである飯田市は長野県南部に位置しており、5月20日(土)に開催された「長野シードルコレクション」の記念すべき第一回目の開催地です。昨年8月開催の「東京シードルコレクション」、11月の「北海道シードルコレクション」に続き3地域目となる「長野シードルコレクション」は、長野県のリンゴ農家やワイナリーなど31社が参加し、49種類のシードルが出品され、用意したチケット350枚は4日前に完売となりました。
Bill氏の訪問先のゴールである飯田市は長野県南部に位置しており、5月20日(土)に開催された「長野シードルコレクション」の記念すべき第一回目の開催地です。昨年8月開催の「東京シードルコレクション」、11月の「北海道シードルコレクション」に続き3地域目となる「長野シードルコレクション」は、長野県のリンゴ農家やワイナリーなど31社が参加し、49種類のシードルが出品され、用意したチケット350枚は4日前に完売となりました。
参加者は、南信地域(飯田市、松川町など)の方を中心に、県外からも40名近くの方が参加され、シードル産地や生産者に対する関心も高まっていることを感じさせられました。ここ飯田市の会場でも、参加者の多くは女性です。20代、30代の女性はスイートを、40代あたりからドライを好まれるようでした。
長野県のシードルは、主にワイナリーがシードルを作っているため、瓶内二次発酵のシードルが多いことが特徴ですが、最近は独自性やこだわりを出すために、複数種類のリンゴをブレンドしたシードル、イギリスやフランスのように果汁を酸化させた黄色がかった色合いと複雑味を持たせたシードル、生食に適さないクラブアップルのみを使用したシードルなども増えてきており、参加者の皆様は多種多様なシードルを、初めて体験し楽しんでいる様子が伝わってきました。

【まとめ】
今回、初めてお会いしたBill氏は、最初の訪問先である楠ワイナリーに向かう車の中で、私に教えてくれました。「今、日本でシードルが盛り上がりを見せていることは、世界の伝統ある国のシードル生産者も注目している。イギリスの生産者も負けずにシードルを広めていこうと良い刺激を受けている」と。この言葉が、今回の取材中、世界各地の生産者とシードルを通じてつながっている感覚を私にもたらしてくれました。
Bill氏は、共著である「World's Best Ciders」に続く第2弾の制作に取り掛かるそうです。おそらく今回取材したシードルの中からいくつか紹介頂けそうです。
日本のシードルが世界各国で紹介され、海外のCiderファンが日本でのシードル・ツーリズムを楽しめる日が来ることを願っています。
(文・写真:小野司、渡部麻衣子)
楠ワイナリー
http://www.kusunoki-winery.com
一里山農園
http://sun-apple.com
いいづなアップルミュージアム
http://www.town.iizuna.nagano.jp/14/111/124/203/1046/000982.html
サンクゼール・ワイナリー本店
http://www.stcousair.co.jp
カモシカシードル醸造所
https://kamoshikacidre.jp
ASTTALシードルクラブ
http://asttal.com
伊那ワイン工房
http://inawine.net
信州まし野ワイン
http://www.mashinowine.com
国際りんご・シードル振興会
http://pommelier.net
