最新記事:2017年12月04日更新
第5回【著者インタビュー】鹿取みゆきさん 「うんちくよりもまず体感できることが、この本の魅力です」
2017年12月04日更新
著者インタビュー第2弾は、『日本ワインガイド』の著者でもあるフード&ワインジャーナリストの鹿取みゆきさんです。日本のワインアロマホイール作成の理由、近年の日本ワインの変化、鹿取さんの夢などについてもお伺いしました。
 鹿取 みゆき(かとり・みゆき)さん
鹿取 みゆき(かとり・みゆき)さん
フード&ワインジャーナリスト。信州大学特任教授。幅広い媒体で日本ワインを紹介する一方で、近年は日本ワインの造り手たちのための勉強会の開催や造り手支援に力を入れる。著書に『日本ワインガイド 純国産ワイナリーと造り手たち』(虹有社)、『日本ワイン99本』(プレジデント社・共著)など。
----改めて新刊書籍『ワインの香り』を手に取ってみていかがですか?
ワインの香りやテイスティングについての本はたくさんありますが、その多くが経験則の域を出ていないため、本当に科学的に正しいのかというと、首をかしげることが多々あります。そうしたなかで、この本はワインの香りを科学的に、それでいて誰にでも分かりやすく説明した本になったと思います。
じつを言うと、香りについては科学的に解明されていないことも多いなかで途中、「科学的に説明していく」ということを、非常に難しいと感じました。科学的に解明されていないことを断定的には言いたくない。でも断定的に言わないとわかりにくくなる。正直に言うと、これは本にするのは厳しいかなと思ったときもありました。
でも最終的には、私たちの踏んだプロセスは正しかった、と思っています。アロマカードを単品のにおい物質にしたこと(個人的にはこれが画期的だと思っています)、実際にどういう言葉が使われているかについて、ワインを造っている現場の生産者にアンケートをしたこと、迷った時に現場に戻ったことが、とても生きていると思っています。
----アロマカードは、ラジオ番組のご出演時(トーキングウィズ松尾堂/NHKFM)や、ワインの造り手のための学校(アルカンヴィーニュ)でも実際に使っていただきました。皆さんの感想はいかがでしたか?
ラジオ番組は、幸運にもワイン業界の人ではない、一般の人に嗅いでもらう貴重な機会になりました。皆さん、どう思うかな? とやや不安を抱きながら本番に望みましたが、ワインからマツタケの香りが感じられること、ゆであずきの香りが感じられること、そしてその香りを実際にカードで嗅げることに、皆さんとてもインパクトを受けていました。うんちくを傾けるよりも、まずは自分の身体で感じられるということが、この本の魅力だということを改めて実感できました。
アルカンヴィーニュの授業では、これからワインを造ろうとしている人たち十数人に使ってもらいましたが、彼らがそれまで漠然と捉えていた香りや言葉だけで知っていた香りを実際に嗅いでもらったことや、1枚のカードが3枚になることで、香りが激変するのを体感してもらったことが、とてもよかったと思います。
またワインの香りを嗅ぎ分けられるようになるという意味では、アロマホイールの付いたテイスティングシート(『ワインの香り』P82)が非常に優れもので、授業でもとても手応えを感じました。私もこのシートを使ってワインを一緒にテイスティングしたのですが、教えるためにかなり神経を使って嗅いだせいか、ワインから本当にいろいろな香りが嗅ぎ取れて、このテイスティングシートは、記録用としても非常に有効だなと思いました。

----なぜ、日本のワインアロマホイールを作ろうと思ったのでしょうか?
常々問題視していたのは、日本ではワインを造る人がいて、それからソムリエがいて、ワインスクールの先生がいて、みんなそれぞれのクラスターの中で言葉を使っていて、それらがほとんどリンクしていないということでした。
醸造家は化学物質名で表現することが多く、またアンケートの結果にも如実に出ていましたが、欠陥と判断される香りには非常に敏感です。一方で多くのソムリエは海外のソムリエたちと共通の言葉を使う傾向があるので、私たち一般の人には馴染みの薄いものの言葉で表現することが多い。ワインスクールも学校ごとにそれぞれ独自の方法で教えている。そのため、同じ香りを表現しようとしても、必ずしも同じ言葉で表現することにはならず、その感覚を共有することができない。
そこで香りを表現する際に全員が共通用語として使えるものが必要だと思いました。それに日本人がワインを表現するのに、何も海外の真似をする必要はないわけで、日本人が日本で暮らす人たちに伝える言葉があっていいなともずっと思っていました。
そして、それをホイールの形にまとめることによって、パッと全体を俯瞰することができる。円形の良さってあるなと思いました。単なる言葉の羅列よりも視認性が高く、また何度も周回してチェックできる。中心から大分類、中分類、小分類と細かくなるので、小分類のひとつひとつの言葉で分かりにくかったら、大分類を見て、例えばフルーティなのか、あるいは花のようなのかを感じてみて、フルーティに感じられたら、さらに中分類の柑橘類なのか、甘い果実なのか、トロピカルフルーツなのかというふうに階層をたどってチェックできる。実際、アルカンヴィーニュの生徒は言葉が探しやすいと言い、香りもたくさん嗅ぎ取れていました。
----香りを記憶する「秘策」はありますか?
声を出して言葉にしてみる。それに尽きます。香りを感じたら、何でもいいから声に出す。全然違いますよ。ぼやっとしていたら、感じた香りはそのままどこかに消えていってしまうけれど、声に出せば香りが言葉として記憶されます。だから誰かと話をしてもいいですよね。香りが共有できれば、さらに楽しいですし。
----続いて、鹿取さんご自身について。まずは信州大学特任教授としての活動・研究について教えてください。
日本でワインを造ろうとしている人を支援するための場や情報の提供をしています。講演会やワークショップを企画したり、海外から研究者を呼んできたりなどですね。研究は、まだ特任教授とワインジャーナリストの二足のわらじなので、なかなか進まないのですが、ワイン産地が形成していくうえで、どういった産官学の連携があるべきなのか、海外の事例も含めて、さまざまなデータを集めて分析をしています。あるいは産地形成のために必要なスキームは何なのかも調べています。それから、各地の気象条件とそこで収穫されるブドウとワインの関連も調べようとしています。
----いつもとても忙しそうですが、それでも精力的に仕事をする鹿取さんの「原動力」は何でしょうか?
原動力はやっぱり、日本各地に造り手たちがいて、彼らが皆、本当に目を輝かせて頑張っていることです。「こんなワインを造りたい」というのを聞いているだけで自分も幸せだなと思えるし、「がんばります」と聞くと、彼らや彼女らを応援しようと思う。日本ワインに関わったから、私の人生は日本ワインと造り手とともにあるって感じです。ホントに。
----そもそも鹿取さんがワインに惹き付けられるようになったきっかけは何ですか?
もともと日本酒が好きで、銘柄によって味が違うなと思っていました。そんなときに、たまたまイタリアのワインを常温で飲む機会があって、そうしたら全然味わいが違って。その次にスミレの香りがするワインを飲んで、ワインってものによって香りが違うんだ、と思ったのがきっかけかなと思います。ただそれだけじゃなくて、中高生の頃は生物部だったので、ブドウ栽培自体にも興味を惹かれました。さらにワインを通して土地が見えたりとか、育てている人の苦労が見えてきたりとか、造っている人の思いが伝わってくるということに、どんどん惹かれていきました。日本のワインに惹かれたのは、それが一番大きいと思います。ワインのいわゆるきらびやかな世界だけだったら、こんなには惹かれなかったと思います。
----2011年に『日本ワインガイド』を出版しましたが、あれから6年経って、日本ワインについて変わったな、と思うことはありますか?
ものすごく変わりましたよね。ワイナリーの数が激増して、2000年以降100軒以上増えている。今年は、もう290軒くらいになっているかもしれません。出版された当時は、まだどこかのワイナリーに勤めていた人が独立して、今では皆が手に入れたいと思うようなワインを造っていたり、その頃はひょっとしたらワインを造ろうと思ってもいなかった人が、ワインを造ろうとしていたり。品種のバリエーションも、ものすごく増えましたし、もちろん品質も向上している。それから、いろいろなお店で飲めるようになりましたね。
----こんなに日本ワインが広がると思っていましたか?
願ってはいましたよね。でもここまで、いろいろなお店で日本ワインが置かれる状況になるとは思いませんでした。地方でも飲めるお店が増えてきましたね。ワインショップやワインバーじゃなくても、居酒屋にも日本ワインがある。それはもう見違えるほどの大きな変化ですよね。
----鹿取さんは、なぜ日本ワインを追いかけ続けているのでしょうか?
毎年ワインが良くなっているし、造り手たちも皆それぞれの場所で、毎年、次はこれをやってみたいとか、今年は何をしようとか考えていて、本当にたゆまぬ努力をしている。それなら、私は彼らのために何ができるだろうと。一生は一度しかないのだから、自分がもし、多少なりとも役に立つのなら、それは代え難いものかなと思います。
----鹿取さんの考える、日本ワインの良さとは?
日本の風土が思い浮かぶこと。例えば北海道の白ワインを飲めば、涼しくて、からっとしていて、爽やかな、土地の印象が思い浮かぶ。
それから海外のワインに比べて、アルコール度数が低いこと。最近では海外のワインは多くが温暖化によってアルコール度数が高く、濃い、強いワインになりがちです。そういう中で、日本ワインは全体として穏やかで、アルコール度数もそこまで高くない。
そしてバリエーションがとても多い。ヨーロッパ系品種からも、アメリカ系品種からも、ヤマブドウからもワインを造っているし、それらの交配した品種からも造っているので、非常に多様性に富んでいる。全体として穏やかなイメージを持ちながら、多様性に富んでいるのが魅力だと思います。
----鹿取さんの夢を教えてください。
日本ワインの造り手たちが、自分たちのおいしいワインを造って、それがもっと多くの人に飲まれることですね。日本ワインの普及率は、まだ日本のワイン市場のたった5%なので、せめて50%までいったら、すごく、すごく嬉しいです。難しいかもしれないけれど。
素晴らしい日本ワインに出会えると、本当に感動するし、そういうワインが、今は1本じゃないですものね。2004年に雑誌『dancyu』に記事を書いたときは、そんなワインを造れる醸造家として3人だけを取り上げましたが、今は心が震えるような日本ワインを造れる人たちが、日本全国に、もう何十人といるわけだから、すごいですよね。もちろん、もっともっと品質の向上は必要だとは思っています。
----ご自身でワインを造ろうとは思わないのですね?
よくそう聞かれるのですが、私は全然そうは思わなくて。だって、造り手たちはみんな一生を掛けて造っているし、そんな彼らの思いが本当に痛いほど分かるから、自分で造るなんて、とても言えない。彼らのワインが飲めれば、それでいいです。
それに私は、自分では造っていなくても、日本ワインの流れの中で彼らと一緒に歩んでいるという気持ちでいます。だから例えまた生まれ変わったとしても、造り手たちを支援する側の立場で、造り手たちと一緒に歩いて行きたい。巡り会えて本当に良かったなと思っています。
----今年飲んで一番おいしかったワインはありますか?
一番おいしかった、これは難しい......。最近、本当にたて続けにおいしいワインを飲んだから......。ついこの間飲んだ「SAYS FARM(セイズファーム)」のアルバリーニョ(品種名)のワインも、いやもう、本当にすごかったです。オレンジピールや、ユズや、アールグレイの香りがして。そのワインがおいしかったので、香港のワインフェアでも、スペインのリアス・バイシャスのアルバリーニョやポルトガルのヴィーニョヴェルデを飲んでみました。でもセイズファームのほうがおいしかった。いや、本当にびっくりしました。
あとは小山田幸紀さん(ドメーヌ・オヤマダ)の「洗馬(Seba)」の白。洗馬は今まで赤しかなくて、今年初めてリリースするワインです。これもすごい。心が震えました。ブルース・ガットラヴさん(10Rワイナリー)の「森」も素晴らしいし、もうとても1本に絞れないですね。
●鹿取さんの「おすすめの本」紹介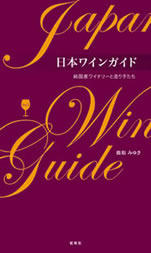 『日本ワインガイド 純国産ワイナリーと造り手たち』
『日本ワインガイド 純国産ワイナリーと造り手たち』
(鹿取みゆき 著/虹有社)
本当に手前味噌ですけど!(笑)、今だに日本ワインガイドは役に立つと思います。例えば、なぜこの土地で、こういう栽培が始まったかだとか、私も忘れてしまっているような話もちゃんと書いてありました(笑)。まだ読んでいないひとにはぜひ読んで欲しいです。
【好評発売中!】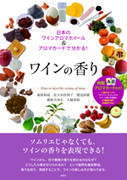 『日本のワインアロマホイール&アロマカードで分かる! ワインの香り』
『日本のワインアロマホイール&アロマカードで分かる! ワインの香り』
(東原和成 佐々木佳津子 渡辺直樹 鹿取みゆき 大越基裕 著)
