最新記事:2018年03月07日更新
第8回【著者インタビュー】佐々木佳津子さん「香りを言葉にすることで日本ワインの地域性や個性をもっと明らかに」
2018年03月07日更新
著者インタビュー第4弾は、北海道・函館の人気ワイナリー「農楽蔵」の醸造家、佐々木佳津子さんです。ワイン造りへの情熱を力に単身フランスに渡り、ブルゴーニュ大学でフランス国家認定醸造士の資格を取得した努力の人。今回のプロジェクトに参加した感想から、ワインにあると嬉しい香り、尊敬する造り手や印象に残るワインなど、さまざまなお話をお伺いしました。
 佐々木 佳津子(ささき・かづこ)さん
佐々木 佳津子(ささき・かづこ)さん
フランス国家認定醸造士。兵庫県神戸市の財団法人神戸みのりの公社「神戸ワイナリー」の醸造担当を経て、2012 年秋に北海道函館市でワイナリー「農楽蔵(のらくら)」を設立。自然の摂理を尊重するブドウ栽培、ワイン醸造を行う。自家農園ブドウを含む北海道産ブドウによる「Nora(ノラ)」シリーズ、「Norapon(ノラポン)」 シリーズなどを造る。
撮影協力:LEVEL神楽坂
----はじめに、本書に掲載されたアロマホイールを作成された感想をお聞かせください。
すごく楽しかったです。でもワインの香りを表現する言葉を絞り込むことは、こんなに大変なのかと思いました。同じ造り手の渡辺直樹さんと私でも、すべてが合致するわけではないし、こんな身近な人たちの間でさえ違いがある。このアロマホイールは、造り手やワインをサービスする人、一般の方に広く使っていただいて、いずれ標準化していけたらと思うのですが、それには時間をかけないといけないなと思います。
----今後、このアロマホイールは、現場でどのように活用できそうでしょうか?
日本ワインの造り手の多くは、香りを言葉で表現することがあまり得意ではないと思います。だから今はまだ、「日本ワインらしい」というだけで、土地の特徴までは区別ができていない。でも北海道で造っているシャルドネと、九州で造っているシャルドネを、どっちもシャルドネらしいよね、と言っていても進化しないので、今後や次の世代のことを考えると、このアロマホイールを元に、各地域で自分たちのワインにどんな香りがあるかについて言葉出しをおこなって、それぞれの地域性や造り手の個性をもっと明らかにしていけたらいいなと思います。北海道なら北海道の、九州なら九州の、またはもっと狭い地域で、それぞれの個性を言葉で表現して、いずれは「九州のこの地域のワインはこういう香りの特徴がある」というところまで、分類できるようになったらいいですよね。
----佳津子さんが造っているワイン(北海道・函館の「農楽蔵(のらくら)」)の特徴的な香りは、どのような香りですか?
「北海道らしい」と言うと、レモンなどの柑橘の香りを代表に挙げる方がとても多いのですが、うちの畑のシャルドネは、柑橘系の香りに加えてパッションフルーツやパイナップル、マンゴーなどのトロピカル系の香りが少しある感じがしています。三笠市や余市町のワインにはトロピカル系の香りはあまりないので、同じ北海道の中でも一番南に位置する地理的な影響があるのかなと思っています。
----アロマホイールにはたくさんの香りの言葉がありますが、個人的にはどんな香りに出会うとうれしいですか?
どの香りも好きですが、特に「火打ち石」の香りはワインに感じるとうれしいですね。「果実」や「花」、「植物」の香りに関しては、品種と造り方で近いものは組み立てられると思うのですが、造りのうえではどうにもならない、その土地のブドウがあってこそ生まれる香りというものがあって、なかでも「火打ち石」はそうだと思います。これはソーヴィニヨンブランのワインに香る可能性が高いのですが、勝沼醸造の甲州ワインのイセハラ(アルガブランカ ヴィニャル イセハラ)にも感じられると思います。 ----続いて、佳津子さんがワインを造ろうと思ったきっかけから、「農楽蔵」を立ち上げるまでを教えてください。
----続いて、佳津子さんがワインを造ろうと思ったきっかけから、「農楽蔵」を立ち上げるまでを教えてください。
実家が建築関係の自営業なので、月に一度の給料日に、職人さんたちが家でお酒を飲む習慣が小さな頃からありました。昔の家の造りで、8畳間がふたつ続いたところに、おじさんたちが何十人と集まって、お酒を飲んで楽しそうに酔っ払って帰って行く。また毎月、神棚にもお酒を供えていましたし、お酒がとても身近だったのです。家で漬物を漬けていたのもあって、もともと発酵食品にも興味がありました。
また兄弟姉妹5人の中で「同じ職業には就かない」という暗黙の了解があって、それぞれ別の道に進んでいるのですが、私はなぜか小さなころからおじさんたちに「かずちゃんは農業だよね」と言われていたんです。実家はお米も作る兼業農家でしたし、生物が好きだったからかもしれません。自然と、お酒や発酵食品造りを学べる学校ということで進路を決めて、東京農業大学の農学部醸造学科に進学しました。そして大学で学んでいくなかで、やはりアルコール飲料を作りたいと思ったのですが、日本酒に関しては、女性はほぼ造りに入れない時代で、いろいろ考えた結果「神戸ワイナリー」に就職することができました。仕事はおもに分析や発酵管理などでした。
----フランスに留学されたのは、就職してからですか?
そうです。自分がワイン造りの道に進むことになって、いざ振り返ってみると、ワインのことを全然勉強できていない。知りたいことを聞ける人もいなかったので、どう勉強したらいいのかさえ、分かりませんでした。それで思い切って、フランス大使館に電話をかけて、「フランスに行ってワイン造りを勉強したいのですが、どこの学校に行ったらいいのか分からないので教えてください」と聞いたんです(笑)。
大使館の人はとてもいい方で、親身になって相談に乗ってくれました。そしてフランスに渡って語学学校に1年間通い、ブルゴーニュ大学醸造学部に入学できたものの語学力が足りなくて、1年生を2回やりました。先生に「大学をやめるか、すべての授業をもう一度受けなさい」と言われて。先生たちも本当に良い人たちでした。そして私が2回目の1年生をするときに、ボーヌのワイン学校に通っていた大越基裕さん(本書の共著者)と佐々木賢さん(ご主人)に知り合いました。
その頃からふたりとも、日本に帰ってやりたいことがある、といっていました。その時フランスに来ていた日本人で、目的があって勉強に来ている人は周りにあまりいなかったのもあって、自然と3人で集まるようになりました。そして、ただただずっとワイン造りの話をしていました。それは多分、ソムリエの立場の大越さんと、ワイン造りとサービスの両方の経験があった賢さんと、ワイナリーに勤めていた私と、それぞれ違う経験を持っていたからこそ成り立っている会話でした。今でもそうですけれども、とてもバランスの良い関係です。でもまぁ当時は、とにかくすごく飲んでいましたけれども(笑)。
それでフランスに4年間いて、2008年の仕込みに「神戸ワイナリー」に戻ってきて2011年まで在籍して、結婚して北海道に引っ越してきたのです。
----北海道にワイナリーを造るのは、以前から決めていたのですか?
私は結婚する以前から独立したいと考えていて、場所は長野県か北海道と漠然と考えていました。運良く賢さんにも出会えたので一緒に土地を探して、結果、見つかったところが道南の今の場所でした。そして畑を立ち上げたころ、知り合いのワイナリーから「ブドウが少し余っているから、売り先を紹介してほしい」と言われて、賢さんが本州のワイナリーに売る手伝いをすることになりました。でも、あまりにもいいブドウなので、これは自分たちでワインを造った方がいいんじゃないか、ということになって「農楽蔵」を立ち上げることになったんです。
ワイナリーを立ち上げた当時は、北海道のブドウでワインを造ったことがなかったので、いったいどういう表現ができるか、その手段をどうにかして作りたいと考えていました。今では日本ワインにも、ナチュラルワインやそれに近いワインが大分多くなりましたが、その頃は、まだそういうワインに対して戸惑っている人が多かったように思います。でも徐々に「あ、こういう表現方法もあるんだね」と変わってきて、今はそれが「おいしい」に結び付くようになった。ワインを飲む人がとても増えたので、懐が広くなったのでしょうか、理解してくれる人がだんだん増えてきて嬉しく感じています。
ですから、今回のプロジェクトのような活動に参加することは、私の中では、とてもいいことだと思っています。ワインの味わいが多様化しているなかで、ただ「おいしい」だけではなくて、みんなが共通の香りの言葉をたくさん持って、どういうふうにおいしいのかを表現することができる。また香りについていえば、もっと食材の「本当の香り」を意識するきっかけになればと思います。今は流通している食材の香りや味が、どんどん薄くなってきているように感じています。例えば、まったくピーマン臭がしないピーマンがたくさんある。ハーブにしても店で売っているものに比べて、野に生えているものの香りは本当に素晴らしい。そうした本当の香りを嗅いだことがあるかないかで、また個々人の香りの表現がずれていってしまうのではないでしょうか。野菜を育てたり、食材の香りを嗅いだり、料理をしたりというようなきちんとした生活があれば、本当の香りに出合う機会は多くなるのではないかと思います。
私たちは、ワインを造って表現していくことが本業ですが、酪農や農業をしている函館の仲間と一緒に、イベントなども行っています。チーズを作っている人、野菜を作っている人、そういう人たちの力が食卓にあってこそ、おいしさの表現はもっと広がるし、また地域内で循環できる食の環境が整っていないと、おいしいものは作れないと考えているからです。今回のプロジェクトのような外からの活動と、仲間との活動とは、最終的にリンクするものだと思っています。
----ではここから、Q&A式に質問を......。
造り手として尊敬している人はいますか?
「10Rワイナリー」のブルース・ガットラヴさんです。発想が豊かで、懐が広くて、寛容で。今も地域の皆さんのためのワイナリーをされていて、そして素晴らしいワインを造る。尊敬しています。
----趣味は何ですか?
趣味は温泉と食べることです。自分で料理をするときは、できるだけ地域のものを使います。生産者が道南にみんないるので、野菜も卵も肉も魚も豊富ですし、直売所や魚屋に行ったり、物々交換をしたりしています。
----佳津子さんの夢を教えてください。
健康(笑)。やっぱり健康ですよね。健全な環境の中で生活して、ずっとワインが飲めて、造れて、おいしいものを食べられてと、一生楽しむために行き着くところは、健康です。
----では最後に、最近飲んで印象に残っているワインはありますか?
ヤン・ドゥリューというブルゴーニュの造り手の「マノン」というワインです。彼は元々「プリューレ・ロック」の栽培をしている人です。ずっと好きで、こういうワインを作りたいなと思っていて。とにかくバランスがいいんです。きちんとした柑橘の香りもあるし、チョークなどの土地の味わいもありつつ、ひとつひとつの香りがすごく凝縮されて締まっている。きちんと円の中に収まっている、という印象です。私はずっとこの人のワインには亜硫酸が入っていると思っていました。亜硫酸を入れないと、この締まりは出ないと思っていたのです。そして一昨年の2月に、彼を訪ねるチャンスがあったのですが、畑もやっぱり素晴らしくて。でも亜硫酸は一切入れていないと言われました。「入れなくても、こういうふうになると思う、俺もよく分からないけど」と。それですごく衝撃を受けました。亜硫酸をまったく入れないで、この味わいを造るのが次のステップなのだということが見えて、いろいろな意味で感動したワインです。
●佐々木佳津子さんの「おすすめの本」紹介 『永平寺の精進料理』
『永平寺の精進料理』
(大本山永平寺・監修、高梨 尚之 調理・執筆)
もともとお寺を巡ることが好きで、精進料理に興味がありました。永平寺を開いた道元禅師が書いた『典座教訓(てんぞきょうくん)』という、禅寺でお料理を作る「典座」という役職の僧への心得が書かれた書物があるのですが、それはとても難しい。でもその精進料理を作るうえでの姿勢や考え方が、とても好きなのです。この本はその教えに基づきながら、もう少し易しく書いてあります。その土地のものを健全な状態で、健全に食べることや、食材ひとつひとつの命を最大限に発揮させることは、ワイン造りや野菜作りにも通じるところがあって、自分たちも植物や食材に対して、そういう気持ちできちんと向き合わなければいけない。それは以前から参考にしているパーマカルチャー※にも繋がっているのではと思います。
※パーマカルチャー(permaculture):環境に負荷をかけず、人間にとって恒久的に持続可能な環境を作り出すためのデザイン体系のこと。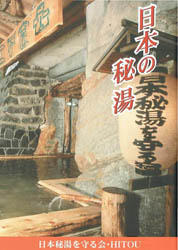 『日本の秘湯』ガイドブック
『日本の秘湯』ガイドブック
(日本秘湯を守る会 発行)
温泉が好きで、社会人になって自由に旅行できるようになったときに買った本です(写真は最新版)。その土地から湧き出るものというのは、本当に素晴らしいと思います。色も香りも違うし、お湯にその土地の味がするのがたまらなく好きです。おいしいワインがたくさんあるのと同じように、温泉もみんなそれぞれ個性がある。温泉とワインは結構、表現が似ているんです。水みたいなお湯だけどミネラルがあるとか、硫黄臭が強いとか、酸化していたり、還元していたりだとか、また浴槽の材質によっては、ヒノキや白檀の香りがあったり、オイル系のお湯は樹脂の香りが強かったり。だから温泉に入って「いいよねぇ、このお湯はヴァン・ド・ターブル的だよね」とか、そういう話をしています(笑)。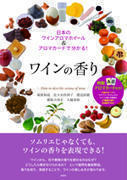 【好評発売中!】
【好評発売中!】
『日本のワインアロマホイール&アロマカードで分かる! ワインの香り』
(東原和成 佐々木佳津子 渡辺直樹 鹿取みゆき 大越基裕 著)
インタビュー撮影協力:日仏バルLEVEL神楽坂
日本ワインとフランスのワイン、そして、おいしい料理を楽しめる神楽坂のお店です。
※『ワインの香り』は、日仏バルLEVEL神楽坂でも販売中です。
<日仏バルLEVEL神楽坂の紹介記事>
http://www.kohyusha.co.jp/nanairo/title/nihonwine/nihonwie07.html
<Facebook>
https://www.facebook.com/nichifutsubaru/
