最新記事:2016年11月20日更新
【第18回】食べ手のプロが選ぶJapan Cheese Award 2016
2016年11月20日更新
国内で行われるワインのコンテストは複数ありますが、チーズのコンテストはおそらくふたつしかありません。ひとつは、第8回の記事で紹介した「ALL JAPANナチュラルチーズコンテスト(略してANC)」(一般社団法人中央酪農会議主催)、もうひとつは、今回紹介する「Japan Cheese Award(略してJCA)」(NPO法人 チーズプロフェッショナル協会主催)です。
ワインのコンテストは、日本ワインコンクールを除けば、輸入ワインも対象であり、日本で造られるものに限っているわけではありません。しかし、チーズのふたつのコンテストは「日本国内で作られるチーズのコンテスト」という共通項があります。どちらも、日本で作られるチーズの品質向上のために始まったコンテストなのです。
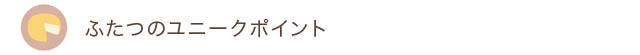
Japan Cheese Award(以下JCA)は、2014年に第1回目が開催されました。ALL JAPANナチュラルチーズコンテストの第1回目が1998年でしたので、後発のコンテストです。NPO法人 チーズプロフェッショナル協会が活動理念に掲げる「チーズに関わる全ての人を応援する」ことと「日本独自のチーズ文化を作る」ことを具現化するために始まりました。
このコンテストの大きな特徴は、ふたつあります。それは「審査員の大半が食べ手のプロ」であるということ。チーズの資格で難関に位置付けられている「チーズプロフェッショナル資格認定」を持っていて、なおかつチーズの品質評価に関するセミナーを受講し、そして審査員となるための味覚の訓練を1年以上(長い人は4年以上)してきた人たちです。
彼ら彼女らは単なるチーズの愛好家ではなく、チーズの食経験がかなり豊かであるということはもちろん、チーズの外観(姿かたち)や風味などを客観的に観察し、その状態について的確な言葉で表現する技術を訓練してきています。そのなかには、チーズの販売に携わっている人、料理研究家、チーズやワイン教室の講師など、日ごろからチーズに関わっている人が多くいます。
そしてこの集団に、チーズの専門家(チーズ製造技術の教官や海外のチーズコンテストの審査員経験者など)と、チーズの生産者が加わり、3〜4名のグループに分かれて協議しながら、ひとつひとつのチーズをチェックしていくという審査方法をとっています。チーズは食べ物ですので、どうしても個人的な嗜好というバイアスがかかってしまいがちですが、グループで審査することにより、ひとりの嗜好に偏った評価にならず、客観性が増して、公平な審査ができるのです。
そしてもうひとつの特徴は、「日本のチーズの品質向上に寄与する」というJCAの開催の趣旨に沿って、コンテストに出品されたすべてのチーズに対して評価の結果報告書を送付することです。審査員は個々のチーズの結果報告書に、例えば「不揃いの小さな穴が上側に多く見られた」、「苦みを強く感じた」などの減点対象となった事項を客観的に捉えて細かく記します。
JCAは、単に賞が取れた、逃したといった勝負の場ではなく、出品した工房に向けて、今後さらなる改善を図るヒントを提案するコンテストなのです。
 日本で本格的なナチュラルチーズ作りが始まってから、まだ30年ほど。今では250軒近くのチーズ工房がありますが、まだまだキャリアが浅い工房もあります。品質は全般的に上がってきたとはいわれていますが、もっと伸び代はありそうです。しかも、日本の風土が作る、日本らしいチーズというものが、まだ確立されていない段階です。単なる人気やブームのおかげで売れることを良しとせず、まさに今こそ、品質を伴って、なおかつ日本人に愛されるチーズを模索していくべき時期なのだと思います。
日本で本格的なナチュラルチーズ作りが始まってから、まだ30年ほど。今では250軒近くのチーズ工房がありますが、まだまだキャリアが浅い工房もあります。品質は全般的に上がってきたとはいわれていますが、もっと伸び代はありそうです。しかも、日本の風土が作る、日本らしいチーズというものが、まだ確立されていない段階です。単なる人気やブームのおかげで売れることを良しとせず、まさに今こそ、品質を伴って、なおかつ日本人に愛されるチーズを模索していくべき時期なのだと思います。そういう大切なときだからこそ、きちんと品質を評価しつつ、食べる側が欲しい、食べてみたいというチーズの傾向を作り手に伝えていくことが必要であり、そうした作り手と食べ手の距離を近づけることが、日本のチーズのファンをさらに増やし、チーズがもっと日本人の食卓にのぼることにつながるのでしょう。
第1回目の開催後、このイベントが日本のチーズ文化を醸成させていくという意味において有効だと、生産者やチーズの業界関係者から評価を受けたこともあり、今年2016年10月に、第2回目が開催されました。
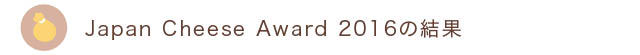 今回のコンテストに出品されたチーズは、65工房の180品(実績ベース)。それらは18のカテゴリーに振り分けられました(本来準備したカテゴリーは19ありましたが、出品なしのカテゴリーがひとつありました)。
今回のコンテストに出品されたチーズは、65工房の180品(実績ベース)。それらは18のカテゴリーに振り分けられました(本来準備したカテゴリーは19ありましたが、出品なしのカテゴリーがひとつありました)。
評価は20点満点(ラクレットタイプを除く)で、「外観」、「生地と組織」、「においと味」を減点法でチェックし、そして特にチーズとして優れている点や汎用性、生産者が意図するコンセプトが表現されているかなどを加点評価で採点します。
合計得点によって「金賞」、「銀賞」、「銅賞」が決まります。得点によって賞が決まるので、ひとつのカテゴリーから同じ賞が複数出ることもあれば、「該当なし」ということもあります。さらに、すべてのカテゴリーで銀賞以上の得点を取ったチーズのうち、最も得点が高かったものが「最優秀部門賞」に選ばれます。そして、すべての金賞受賞チーズの中から、ひとつだけ「グランプリ」を決定します。
結果は、以下のようになりました。
 【グランプリ】
【グランプリ】
森のカムイ ハッピネスデーリィ(北海道)
【金賞】
フロマージュ・フレ ファームQ(熊本県)
リコッタ SHIBUYA CHEESE STAND(東京都)
リコッタ ダイワファーム(宮崎県)
リコッタフレスカ IL RICOTTARO (岡山県)
ココン アトリエ・ド・フロマージュ(長野県)
ブルーチーズ 二世古 空【ku:】 ニセコチーズ工房(北海道)
ブルーチーズ アトリエ・ド・フロマージュ(長野県)
ジャパン ブルー 冨田ファーム チーズ工房(北海道)
山羊のハイジ 三良坂フロマージュ (広島県)
まきばの太陽 高秀牧場 ミルク工房(千葉県)
オールドゴーダ 木次乳業(島根県)
コハク・クミン 糸島ナチュラルチーズ製造所 TAK(福岡県)
タカラのトケル チーズ工房タカラ(北海道)
幸 しあわせチーズ工房 (北海道)
【銀賞】 39品
【銅賞】 54品 *詳細な結果一覧は、チーズプロフェッショナル協会のサイトをご覧ください。
*詳細な結果一覧は、チーズプロフェッショナル協会のサイトをご覧ください。
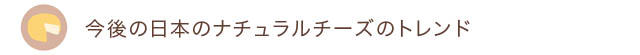
チーズの出品傾向やその数量、そして出品工房の地域などから、日本のナチュラルチーズの今が如実に見えてきます。出品されたチーズで目立って数が多かったのは、フレッシュタイプとパスタフィラータタイプ(モッツァレラなど)でした。
もうすっかり市民権を得ているモッツァレラをはじめ、フレッシュタイプのチーズは程よい酸味もあるため、ヨーグルトにはすっかり馴染んでいる日本人の食卓には、登場しやすい、普段使いのチーズとなりつつあるのでしょう。
とくに今回はリコッタの出品が多く、前回の倍以上に増えました。東京などの大都市圏では、国産のリコッタはあまり見かけないだけに、こんなにも多くの工房で製造されているのかと驚きました。チーズ製造で必ず排出され、捨ててしまうことになるホエイを利用して商品にするリコッタは、鮮度が命。大半が現地で消費されているのでしょう。また優しい甘みが特徴の穏やかな風味から、おそらくどこの工房でも人気商品で、全国から自慢のリコッタが集結したという感がありました。
またモッツァレラの生地を袋状にして、モッツァレラカードを細かく刻んで生クリームと和えたフィリングを包み込むブッラータは、まるで「チーズの巾着袋」。しばしばメディアに取り上げられることもあってか、今回は出品が倍以上に増加しました。このチーズの流行はしばらく続きそうです。
地域別に見てみると、熟成期間が長い圧搾タイプのカテゴリー(コンテストでは非加熱圧搾、加熱圧搾というカテゴリーになる)に出品されたチーズの大半が、北海道で製造されているものでした。とくにここ数年、"ハイジに出てきたチーズ"として、すっかりおなじみになったラクレットタイプに出品されたチーズはすべて北海道。この傾向は、やはりチーズの長期熟成に適した北国という気候ゆえのことか、チーズ製造の歴史が長い地域だからか、それとも製造から熟成と高度な技術を要するチーズを作る工房が多いのか......。
いずれにしても、チーズのタイプに地域性が現れてきているというのは、「土地の味を表す発酵食品」というチーズの本質に近付いてきているのかもしれません。日本のナチュラルチーズも創成期から少し抜け出し、発展期に入りつつあるような、そんな兆しが見えたコンテストでした。
写真提供:チーズプロフェッショナル協会

