最新記事:2015年12月20日更新
【第8回】ALL JAPANナチュラルチーズコンテスト
2015年12月20日更新
このWEBマガジンの第1回で、日本のナチュラルチーズ製造の歴史について少し触れていますが、日本のチーズ工房の軒数は1990年代から急激に増えました。当時はまだ食生活の中にナチュラルチーズが根付いていなかったこともあり、手探りで製造している工房が多く、ヨーロッパのチーズをお手本に作り、名前もそのまま引用した(例えば「カマンベール」や「ゴーダ」など)ものが大半でした。
そんな中、国産のチーズの品質向上、販路拡大を目的とした国産チーズのコンテスト「第1回ALL JAPANナチュラルチーズコンテスト」(主催:一般社団法人中央酪農会議)が1998年に開催されました。その後、同コンテストは隔年で開催されるようになり、今年の11月に第10回が開催されました。
今回、審査員を務めてきましたのでコンテストの様子などをレポートします。 写真:審査をする佐藤優子さん(右)
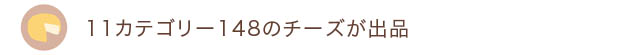
第1回のコンテストが開催された当時は、ナチュラルチーズを製造する工房は全国で76軒ほどしかなく、記念すべき第1回目に出品されたチーズは79アイテムでした。
それが17年経った今では、工房数は全国で220軒以上になり、今回のコンテストではチーズの数も148アイテムと、カテゴリー数も11部門と格段に増えて、国産チーズの生産の拡大やバラエティの広がりが数字にも表れています。審査方法、チーズのカテゴリーの分け方などは、その時々の事情に合わせて改正があり、現在に至っています。
今回、出品された148品のチーズは、以下のカテゴリーに分けられ審査されました。
1 フレッシュ部門 26品
2 パスタフィラータ部門 42品
3 ソフト部門 7品
4 白カビ部門 11品
5 ウォッシュ部門 6品
6 青カビ部門 3品
7 シェーヴル部門 9品
8 ハード3カ月未満部門 10品
9 ハード6カ月未満部門 11品
10 ハード6カ月以上部門 10品
11 トライアル部門* 13品
(*トライアル部門とは2014年11月以降に販売を開始したもの、または未発売のもの)
出品数を見てみると、パスタフィラータ部門の数が多くなっています。同部門の中で、特にモッツァレラが24品もエントリーされていて、北は北海道、南は九州まで、全国各地の工房で製造されています。
コンテスト終了後に、エントリーした工房名を見たところ、規模の大きな乳業会社が作っているものもあれば、小さな工房がひとつひとつ手作りをしているものまで多種多様です。イタリアのチーズ工房で研修経験のあるメーカーが手掛けたものや、水牛乳製のものまでありました。
モッツァレラが今や、日本の食卓ではそれほど珍しいものではなくなり、気軽に買って楽しめるチーズになっているということなのでしょう。
そして、このコンテストが始まった17年前には、ほとんどなかった6カ月前後あるいはそれ以上熟成したハードタイプのエントリーが多くあり、熟成に耐えうるチーズ造りと確かな熟成の技術が向上しているということを強く感じました。
これらのチーズは、ほとんどが北海道産。北海道は乳量が豊富ということもありますが、日本におけるチーズづくりの歴史が長く、技術の蓄積がなされているということなのだと思います。
審査はもちろん、すべてのチーズのパッケージを外し、ブラインドで行います。大きなチーズも基本、ホール(ひとつまるまる)で出品され、スタッフによってその場でカットされます。つまり出品者もチーズの中の状態を目視で点検をすることなく出品するのです。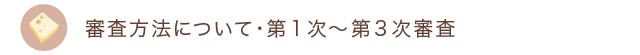
このコンテストの審査は、第1次審査から第3次審査は非公開で行なわれ、最終審査はステージ上での公開審査となり、最高賞に当たる農林水産大臣賞などの受賞チーズが決まります。
まず第1次審査では、出品されたすべてのチーズをカテゴリーごとに順番に2人の専門家(学術研究者とチーズ製造経験者)が丁寧に品質をチェックしていき、最終的に60アイテムのチーズを選定します。 第2次審査では、また別の5人の専門家(販売、コンサルタント、メーカー、研究者、料理人)が審査に当たります。60アイテムをひとつひとつチェックし、「外観・色調」、「組織」、「風味」の3つのポイントで点数を付けていきます。5人の点数を合計し、合計点の高かったものから20アイテムが第3次審査へと進みます。
第2次審査では、また別の5人の専門家(販売、コンサルタント、メーカー、研究者、料理人)が審査に当たります。60アイテムをひとつひとつチェックし、「外観・色調」、「組織」、「風味」の3つのポイントで点数を付けていきます。5人の点数を合計し、合計点の高かったものから20アイテムが第3次審査へと進みます。
ここまでの第1次、第2次審査で、チーズとしての完成度の高いものを選抜することになります。
第3次審査はさらに審査員の数が増え、9名の審査員(料理人、バイヤー、研究者、メーカー、マスコミ、俳優、サービス、その他)が20アイテムの中から、それぞれの目線で優れたチーズをひとつ選びます。
例えば、料理人である審査員はリコッタチーズを選びました。
その理由は「チーズとしての味わいはもちろんだが、料理の素材として利用価値が高いもの、という観点で選ぶと、このリコッタは最適である」とのこと。
また大手スーパーのバイヤーである審査員はラクレットタイプ(熱でチーズを溶かして利用することもできる)のチーズを選び、「店舗での販売を考えると、野菜などとの組み合わせでメニュー提案ができるチーズであるのが魅力だ」と言っていました。
このように第3次審査以降は、消費者のニーズに敏感な立場の審査員が携わることにより、今、市場で求められているチーズが選ばれます。
こうして9つのチーズが最終審査に進みます。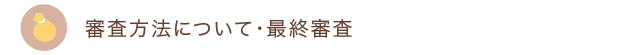
そして最終審査は、ステージ上での公開プレゼンテーション審査となります。
第3次審査に当たった審査員がひとりずつ、自分の選んだチーズの魅力や利用法などをプレゼンテーションした後、9名の審査員が5点満点で得点を付けます。9つのチーズのうち合計得点の高いものから、「農林水産大臣賞」、「農畜産振興機構理事長賞」、「中央酪農会議会長賞」が選ばれます。
また第3次審査まで進んだ20のチーズのなかから、2点が「審査員特別賞」、7点が「金賞」、8点が「優秀賞」を受賞しました。
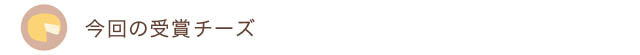
【農林水産大臣賞】 「大きなチーズ」
「大きなチーズ」
(白カビ部門)
有限会社エイチ・アイ・エフ 長野県
【農畜産振興機構理事長賞】 「森のカムイ」
「森のカムイ」
(ハード熟成6カ月以上部門)
有限会社ハッピネスデーリィ 北海道
【中央酪農会議会長賞】 「水牛乳で造ったリコッタ」
「水牛乳で造ったリコッタ」
(トライアル部門)
株式会社箱根牧場 北海道
【審査員特別賞】 「りんどう」
「りんどう」
(ウォッシュ部門)
有限会社那須高原今牧場 栃木県  「牛鐘(カウベル)」
「牛鐘(カウベル)」
(ソフト部門)
有限会社ランランファーム 北海道
【金賞】
「さくら」(ソフトタイプ部門) 共働学舎新得農場 北海道
「ラクレット」(ハード3カ月未満部門) 共働学舎新得農場 北海道
「鶴居ゴールドラベル」(ハード6カ月未満部門) 株式会社鶴居村振興公社 北海道
「ラクレット」(ハード3カ月未満部門) 有限会社NEEDS 北海道
「サントモール」(シェーヴル部門) 一般財団法人水戸市農業公社 森のシェーブル館 茨城県
「茶臼岳」(シェーヴル部門) 有限会社那須高原今牧場 栃木県
「フロマージュ・ド・みらさか 牛」(ソフト部門) 三良坂フロマージュ 広島県
【優秀賞】
「リコッタ フレスカ」(フレッシュ部門)株式会社ファットリア・ビオ北海道 北海道
「鶴居シルバーラベル」(ハード熟成3カ月未満部門)株式会社鶴居村振興公社 北海道「リーレツルイ」(ハード熟成6カ月未満部門) 株式会社鶴居村振興公社 北海道
「蝦夷農カマンベール」(白カビ部門) 株式会社十勝野フロマージュ 北海道
「槲(かしわ)」(ハード熟成6カ月未満部門) 有限会社NEEDS 北海道
「プローヴォラ」(パスタフィラータ部門) イル リコッターロ 岡山県
「クリームチーズ」(フレッシュ部門) 上ノ原牧場有限会社カドーレ 広島県
「ロビオーラ ダイワ」(ウォッシュ部門) ダイワファーム 宮崎県
国産ナチュラルチーズの歴史はまだ浅いとはいえ、この20年弱の間に着実に技術が向上し、私たちの食卓にも定着しつつあるという実感を得ることができました。
これから先の20年、いったい日本のナチュラルチーズはどのように進化していくのでしょうか? 日本の風土や食文化が風味などに反映された日本独自のスタイルが確立し、「JAPANESE CHEESE」というジャンルとして海外の人にも食べてもらえていたら......と期待せずにはいられません。
写真提供:チーズプロフェッショナル協会
