最新記事:2017年01月20日更新
【第20回】Let's Cheese Tasting!!~チーズを覚えたい人のために~
2017年01月20日更新
「チーズに関する仕事をしています」と、新たに知り合いになった人に自己紹介をすると、かなりの確率で「チーズは好きなんですが、よく分からないので教えてください!」と言われます。まあ8割がたは社交辞令だとしても、日本人にとって、チーズは種類が多くてよく分からない、未知の食べ物なんだ、というニュアンスは伝わってきます。
海外から輸入されたナチュラルチーズを自宅で食べるために店頭で購入しようと思ったけれど、何を買ったら間違いないのか分からないので、買うことを諦めた、なんて体験談もよく聞きます。
私は仲の良い友人たちの集まりなど、機会があるたびにチーズを数種類持って行き、簡単に説明をしたうえで楽しんでいただくのですが、結局「チーズっておいしいねぇ〜」で話が終わってしまい、どのチーズがどうおいしかったかという記憶はさっぱり残らない、なんてことになります(一緒にお酒もたんまり飲んでいることが原因かもしれませんが)。
「そろそろチーズ初心者から脱して、せめてチーズ初級者になりたい!」という人には、ぜひ「チーズのテイスティング」を実践してほしいと思い、今回はその進め方を紹介いたします。
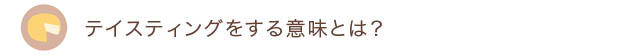
「テイスティング」は、直訳すれば「試食」ということになりますが、もともとチーズのテイスティングは、「試食」を通してチーズの出来を確かめることと、それらが持つ風味の特徴を言葉で表現し、他者とコミュニケーションをとることが目的です。
しかしテイスティングをする人の立場の違いにより、若干目的が変わってきます。
まず、チーズをひとにすすめる職業についている人たち(例えばチーズの販売員やレストランのサービス担当など、チーズのプロと呼ばれる人たち)の場合、扱っているチーズが商品として適正な価値があるのかどうかを確認し、さらにチーズの味わいの特徴など、商品を購入する手がかりをお客さまに提供するためのテイスティングが必要となります。
チーズを製造している人にとっては、商品としての適正な価値があるかを判断することはもちろんですが、ちょっとした欠点を客観的に捉え、安定した商品を作り続けるために、ブレを調整していく見極めをテイスティングによっておこないます。
そしてチーズの食べ手である私たちは、店頭に並んだ多くのチーズから、自分の目で食べごろや味わいなどを判断し、自分の好みにあったチーズを選ぶ技術を身に付けるためにテイスティングをします。それは、その場限りの単なる「試食」ではなくて、自分の舌に経験値として刻み込むような意識的なテイスティングである必要があります。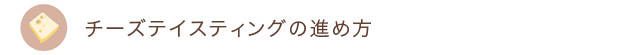
意識的なテイスティングを実践すべく、テイスティングの方法について説明しましょう。
ワインのテイスティングと同様に、チーズのテイスティングにも進め方があります。これからご紹介する方法は、フランスなど海外でのテイスティングの手法を参考に、チーズプロフェッショナル協会で構築されたもので、チーズの専門家および一般向けのセミナーや勉強会などで広く使われています。
[チーズのテイスティング方法]
①〜③の順に(②と③は同時に)、3段階に分けてアプローチしていきます。
①「外観」から情報を得ます。
ここでは対象となるチーズはどのような形状か? 外皮の質感や色は? カットした状態であったなら、そのカット面の質感や色は? など、視覚から得られる情報を客観的に捉えます。
その外観の状態が何を表しているのか、というところまでは、はじめから読み取ることはできなくても、経験を積んでいくと「この見た目だと熟成状態はこのくらいかな、味わいはこんな感じではないかな」と、大体の想像がつくようになります。 (コメント例)
(コメント例)
真白な雪のように生え揃った白カビ
(カットしたピースを見て)
カット面、なめらかでバターのような濃い黄色い組織と中心部にはチョーク状の芯がある
②「テクスチャー(組織)」を見ます。
触感(あるいは食感)をチェックします。チーズの質感、硬さや弾力を指などで触り、次に口の中に入れて歯応え、舌触り、溶け具合、粘性などを感じます。口の中でほどけるように溶けるもの、しっかりと咀嚼しないと飲み込めないものなど、同じタイプのチーズでもテクスチャーが違うものがあります。自分の好む、おいしいと感じる食感はどんなものなのか......と自分自身にも意識を向けてみましょう。
 (コメント例)
(コメント例)
外から触るとカビに指紋が付くくらいフサフサとしている
指で触ると弾力はほとんどなく硬めなテクスチャー
バターのように口中の体温で溶けていく食感
芯の部分はボソボソとした食感
外皮(白カビ部分)はコリコリとした歯触り
③「風味」を確かめます。
「風味」とは、味と香り、そして余韻などを指します。
口の中に入れて舌で感じる、いわゆる「五味(甘、塩、酸、苦、旨)」と口中の粘膜で感じる「刺激(渋み、収斂み、辛み、えぐみ)」の有無を客観的に捉えて、そのバランスがどんな具合かを感じ取ります。そしてチーズに鼻を近付けて感じる香り、ごくんと飲み込んでから鼻腔に広がる香りなどをチェックします。
チーズの場合、可食部ではない外皮(食べられる外皮ももちろんありますが)の香りも特徴があることが多いので、その部分の香りのチェックも忘れずに!また食べた後に残る余韻の長さもチェックポイントになります。
 (コメント例)
(コメント例)
マッシュルームのようなキノコの香り
温めたミルク、あるいはバターのような香り
塩気をあまり感じなくてマイルドな印象
ひと口目はバターのような濃厚さがあるが、後味は意外にあっさりしている
以上のポイントをメモ書き程度に、例えばスマホの日記アプリにでも写真とともにあげておけば、あとから自分で見返すことができ、備忘録になります。
ナチュラルチーズはプロセスチーズと違って、微生物の働きによって日々味わいが変化しています。たとえ同じ名前のチーズを食べたとしても、全く同じということはありません。しかもその種類は数え切れぬほど......。しかしチーズの特徴を捉えながら意識して食べるだけで、チーズの名前やその時の印象が案外記憶に残っていくものです。
前回食べたカマンベールは、白カビが元気で味はあっさりしていたけれど、今回のカマンベールは、白カビが少しくすんでいて味が濃い、なんて経験を重ねるうちに、「自分はこれくらいの熟成のカマンベールが好き」と自分の好みもはっきりしてきます。
テイスティングを通して、自分自身の中にチーズの食体験の蓄積をしていけたら、市場に並ぶ魚や野菜を選ぶように、チーズショップに並ぶチーズの状態を見ながら、その日の気分でチーズを選ぶことができるようになるでしょう。一緒に食べる人の顔を思い浮かべながらチーズのセレクトができるようになったら素敵だと思いませんか?
