最新記事:2015年07月25日更新
第7回【豊穣の海・東京湾のサバとは その一】
2015年07月25日更新
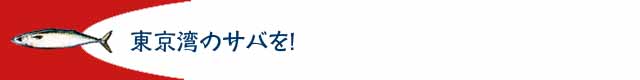
みなさば、こんにちは。
サバニスト小林です。毎月連載の予定が、なんだかんだ間が空いてしまいました。もう夏です。毎日暑いですが、旨いサバでも食べて夏を乗り切りましょう!
はてさて、久しぶりの更新となる今回より数回連続で「東京湾のサバと東京湾」について書いてみたいと思います。
「東京湾でサバが獲れるんか?」とお思いの方も多いかもしれませんね。
サバというとついついブランドサバを思い浮かべてしまいがちですが、少し視点を変えて都会の海に目を向けてみましょう。東京湾も海ですからね、サバはいるんです。しかもちょっと驚きの旨さ!

どーん! いきなりですが東京湾のサバです。しかも刺し身です!皮目の脂を見てください!脂がのってますね。ふらっと入った内房のとあるお店で、まさかこんなサバに出会えるとは思ってなかったです。嬉しい驚き。
ほかに、サバ漬寿司も。うーん、いいぞ、旨いぞ。サバ漬寿司は少し甘みのある味付けがちょうどよい。自分でシャリの上にのっける食べ方も新鮮。こちらはゴマサバですな。ご飯はおかわりです。
さらに、下の3つの写真をご覧ください。


上から順に、ウルメイワシ刺、イカ刺、イカかき揚げ丼(一人で全部食べたわけではありません 笑)。
ところで、これぜーんぶ東京湾で獲れた魚なんですよ。ブランドサバ もちろん旨いけど、東京湾のサバも旨いじゃないですか。灯台下暗しとはこのことか。ウルメイワシもイカも旨かった。
ちなみに、食用として流通している魚種が一番豊富なのは東京湾なんだそうです。知ってました? 私は知りませんでした。
では、東京湾はいったいどんな理由で魚種が豊富なんでしょう?
そしてサバが旨いんでしょう?
海洋ジャーナリストの森山利也さんに聞いてみました。
 6月末、東京湾の謎を紐解くべく森山利也さんを訪ねてふらっと富津へ。都内からアクアラインを通ってバスで1時間半ほど。意外と近い。小旅行気分にはちょうど良い距離感です。
6月末、東京湾の謎を紐解くべく森山利也さんを訪ねてふらっと富津へ。都内からアクアラインを通ってバスで1時間半ほど。意外と近い。小旅行気分にはちょうど良い距離感です。
森山さんはまず、富津岬へ連れて行ってくださいました。展望台らしきものがあり、ここから東京湾を見下ろすと横浜方面も見渡せます。すっきり晴れると富士山も見えるそうです。 ところで東京湾ってどこからどこまでなんでしょう?
ところで東京湾ってどこからどこまでなんでしょう?
狭義には、三浦半島の観音崎と、ここ富津岬を結んだ北側が東京湾だそうです。
また広義には、浦賀水道を含む海域を指すそうです(三浦半島の劔崎と房総半島の洲崎を結んだ北側)。
ということは、富津岬の北側が狭義の東京湾、南側が広義の東京湾。
左の地図で見ると、ピンク色の部分が狭義の東京湾、ピンクと水色の部分が広義の東京湾です。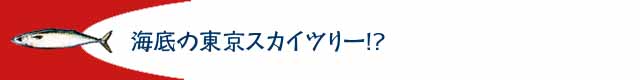
保田方面に南下していくと鋸山という山があります。
名前の通りノコギリの歯のように尾根が続くかたちの鋸山はロープウェーで登れ、頂上からの眺望は素晴らしいそうです。そして東京湾の深いところは鋸山のおおよそ倍の深さの谷があり、最深部は660mとか。東京スカイツリーは634mですから、ちょうどすっぽり入っちゃいます。
ちなみに狭義の東京湾の平均水深は17m程度とのこと。
要するに、富津岬 -- 観音崎の南北でずいぶんと海底の地形が違うのです。
南側では大型回遊魚が見られ、クジラも回遊することがあるとか! 逆に浅い北側には干潟が点在し、魚介類の稚魚の生息地となっているそう。
東京湾には浅いところに棲む魚と深いところに棲む魚がいるっちゅーこっちゃ!
いろんな種類の魚がいるっちゅーこっちゃ! 近くて遠いなー。
近くて遠いなー。
実は知らないことだらけだな、東京湾。
私は、横浜在住なので一番身近な海だけど、都会の河川の汚れとか、とかくそういうマイナスなイメージに陥りがち。そこが豊穣の海だったとは知らなかったです、お恥ずかしいかぎり。ついつい遠い地域の海に旨い魚を追い求めてたけど、東京湾の魚も旨かった! サバも旨かった!
そうそう、なんで旨いのー?という話しを。
あんまり詳しく書くと長くなるので、大まかに3つ挙げます。
①流入河川の多さ
②干潟の存在
③海流
少しずつ解説。
まず、①流入河川と②干潟について。
東京湾に流れ込んでいる主な川は、多摩川、荒川、鶴見川など。それらは、山の雪解け水をはじめ真水をじゃんじゃん運んできます。その水には有機物がたくさん含まれていて、それらはどどーっと干潟に流れ込んで栄養になり、中学生で習った食物連鎖を生み出します。
植物プランクトン → 動物プランクトン → 貝やエビ、カニ → 小さな魚 → 大型の魚、という感じ。
つまり豊富な真水と、干潟が残っていることが栄養を育み餌が豊富な海を作っているんですね。これがポイントです。
次に③海流。
黒潮がぐるぐるっと反時計回りに入ってきてまして、意外に潮の流れが早いそうです。
潮の流れが早いと、魚の運動量が上がる。運動してるだけだと痩せちゃうけど、そこには餌が豊富にあるので育ちやすいと。
東京湾の魚は自然に運動もしてるし、しっかりと食べてる。人間で言うと健康的な感じですね。若干羨ましい。
ほかにも岬の名前や地名の由来、干潟など、いろいろと興味深いお話しを伺って帰路につきました。
東京湾のサバ。
旨さの秘密には複合的な理由がありました。
地形や河川や海流など様々な自然条件がばちぃっと揃った、かなり奇跡的な海なんじゃないのか?! 東京湾。
次回は、東京湾のサバを釣ってみれたらなと考えています。
■今回お話を伺った森山利也さんのプロフィール
海洋ジャーナリスト、フォトグラファー、そして料理人であり、プロアングラー(釣り)。
漁師がつくる社会起業集団である株式会社エンジョイ・フィッシャーマンのアドバイザーをつとめる。
新聞や雑誌への寄稿、連載も多数あり。
20代半ばで有名旅館の料理長に。その後26歳で自身の店「はいから屋」をオープン。同時にプロアングラーとして世界の海で魚を追いかけた経歴も持ち、震災後は店を閉じ、東北に船を運んだりのボランティアに。
現在は築地を中心に、魚のさばき方、手間のかからない調理方法を伝授する人気の料理教室を開催。 クックパッドでもレシピ検索ランキングでトップ10入りしている。
写真協力:KerisMoriyama

