最新記事:2014年12月25日更新
第4回【サバとクリスマス】
2014年12月25日更新
ずいぶん寒くなってきましたね。
もう新しい年が目の前、サバも必死に脂をのせているところですが、その前に一大イベントの到来です。今年もやってきてしまいました。そう、今日は、クリスマスです。すでに明暗がわかれているかもしれませんが、憧れの彼女とのデートで、緊張してうまく会話ができないサバ好き男子はいませんか。女子心をくすぐる、しゃれたうんちくのひとつやふたつ、事前に用意しておくのが男のたしなみです。
ということで、きっとデートに役立つ、サバのうんちくを大公開します。
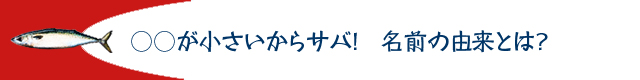
さて、サバのうんちく一つ目。
サバはなぜサバと呼ばれるようになったのでしょう? サバの語源についてです。名は体を表すと言いますが、やはり体の特徴が語源である説が有力なようです。江戸中期の語源辞書『日本釈名』などによれば、サバの体の何処かが他の魚に比べて小さいことに由来し、サはささやかの意、小◯(サバ)であると記されているそうです。
ぬぬ、では何処が小さいのでしょう? 目は大きいですし、見た目も小さくはありません。スーパーに並ぶ切り身ではわからないですが、海釣りをする方はご存知かもしれませんね。それは歯なんです。歯が小さいため、小歯(サバ)だそうです。どれどれ、たしかに小さいですね。
他説として、群れる・多く集まる魚なので「多(さわ)」から転じたという説もあるそうです。
ちなみに、現在の漢字"鯖"は青い魚ですね。青いのは背ですが、これが保護色と言いますか、海の上から見ると波間に紛れてしまうのです。それで海鳥など空から狙ってくる捕食者の目をくらますんですね。あの特徴的な素敵な模様も波間に溶け込むのに役立ちそうですね。 腹側にも秘密があります。あの白色から銀色に輝く腹は、海面のキラキラに紛れるため、下から狙う大型魚から身を守るそうです。
さぁ、サバサバと二つ目にいきましょう。 日本人に馴染みの深いサバ、最古の文字資料は奈良時代とも平安時代とも言われていますが、江戸時代には、七夕の前後に諸大名が将軍家へサバを献上する習慣があったそうです。それが後にサバ代としてお金で納めるようになり、これがお中元の習慣になったとも言われているとのこと。将軍様もサバを食べていたと。大昔から人気者だったんですね。 
そんな人気魚であるサバは食べるだけでなく、各地で信仰にも用いられてきました。神奈川県にも鯖神社が複数あったり、徳島県には鯖大師本坊とよばれるお寺まであるんです。
鯖大師には鯖断ち祈願なるものまであるとのこと。気になって気になって仕方がないので、サバニストは徳島県へ行ってみました!  四国八十八箇所は、四国にある空海(弘法大師)ゆかりの88か所の寺院の総称です。鯖大師本坊と呼ばれる八坂寺は、88か所の他に空海さんが残した数多くの足跡のうち20の寺院によって霊場とされた四国別格二十霊場にあたります。
四国八十八箇所は、四国にある空海(弘法大師)ゆかりの88か所の寺院の総称です。鯖大師本坊と呼ばれる八坂寺は、88か所の他に空海さんが残した数多くの足跡のうち20の寺院によって霊場とされた四国別格二十霊場にあたります。
室戸岬から2時間ほど車で走ると鯖瀬(さばせ)という駅があり、そこから歩いて数分の距離に八坂寺はあります。
なぜ鯖大師と呼ばれているのでしょう?
寺務所で尋ねてみました。すると、その縁起が絵と文章で解説されている書画が本堂にあるから入って見てごらんとのこと。入らせていただくと部屋をぐるりと囲むように9枚の額が順番に飾られていました。
それらによると、空海の修行中、行基菩薩手植えの松の下で野宿し行基の夢を見たところから話が始まります。
ある朝、塩鯖を馬の背に積んだ馬子が通りかかり、空海が塩鯖を所望したところ、馬子は鯖をあげずにののしり立ち去った。すると難所で馬が急に倒れ動かなくなった。馬子は先ほどの僧は空海に違いないと思い、空海に鯖を差し出し馬を治して欲しいと懇願します。空海が加持水を馬に与えたところ、馬はたちどころに元気になった。さらに、空海が法生島(ほけじま)で先ほどの塩鯖にお加持して海に放ったところ塩鯖は生き返り泳ぐ。これに感服した馬子は、空海に教えを受け、この地に庵を建て鯖大師の霊験を今に伝える。
という空海の伝説が由来となっています。  そのため、大師堂というお堂の前には、石で作られたサバ(背の模様がリアルに表現されている)、それからなんとサバを手にした弘法大師が安置されているのです。
そのため、大師堂というお堂の前には、石で作られたサバ(背の模様がリアルに表現されている)、それからなんとサバを手にした弘法大師が安置されているのです。
もうひとつ。鯖大師には鯖絶ち(断ち)三年祈願があります。ネット断ちやゲーム断ち、酒や煙草など、断ち物の対象はさまざまかと思いますが、いくら願掛けと言っても鯖断ちというのは聞いたことがありません! サバ好きの我々には効果絶大かもしれませんが、いやほんとにサバを、しかも三年もっ!
鯖絶ち祈願はしませんでしたが、ちょうど今年は四国霊場開創1200年にあたるということで、販売されていた記念絵葉書をもちろん購入し、ひとしきり満足感に包まれながら、気持ちを新たに帰途につきました。
どうでしたか! これで憧れの彼女ともサバ話で盛り上がって、うまくいくこと間違いなし!素敵なクリスマスをお過ごしください(盛り上がらなくても私のせいではありませんので悪しからず)。
※次回の更新は、2月25日になります。お楽しみに!

